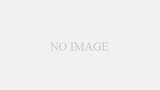ステフィン・カリーの身長
ウィングスパンや身長など、遺伝的な要素が非常に重要なNBAの世界の中でも、身長188cm と小柄なゴールデンステート・ウォリアーズのステフィン・カリー。
サイズ的ディスアドバンテージを背負った彼がどのようなトレーニングを行い、4度のNBAチャンピオン&ファイナルMVPまで上り詰めたのか。
今回は、過去に約10年間、カリーの専属スキルコーチを担当していた、ブランドン・ペイン氏がGQ Sports にて紹介しているインタビューを元に、一風変わったトレーニング方法とその効果について紹介いたします。サイズ的にあまり大きくない彼は、脳機能や視覚を鍛えるトレーニングなど多く取り入れているため、日本人の私たちにも非常に参考になる内容となっております。
カリーのウォームアップドリル
NBAファンやバスケファンの方は、一度は見たことのあるカリーのウォームアップ。ボールを2つ使ったドリブルや、独自のシュート練習などを行っているのは、お馴染みです。
ウォームアップドリルの他にも今回参照にした GQ Sports でのトレーナーへのインタビューでは、マルチタスクでのドリルが紹介されております。
1、ドリブル + テニスボール
片手でドリブルを行いながら、テニスボールを宙へ投げたりなど
2、ドリブル + テニスボールドリブル
両手でレッグスルードリブルを行いながら、テニスボールもワンバウンドさせ、ドリブル。
3、ドリブル + テニスボール+α
2のドリルへの対応力が高まったところで、両手レッグスルードリブルなどを加えながら、テニスボールの壁当てなど行います。
バスケットボールをドリブルしながら、テニスボールを空中に浮かせるなどをして、複数のタスクを同時に行い、複雑な情報を脳に与えて負荷をかけています。これによって、あらゆる要素が組み合わさるゲーム内の状況下においても、適切な判断やパフォーマンスが可能になります。
その科学的効果
近年の研究は、アスリートとアスリートではない人を比べると、様々な要素が組み合わさった複雑な状況下での、注意コントロール能力は、やはりアスリートの方が優れていることが示唆されています。(1)
反応速度が違ってくるのは、皆が周知の事実でしょう。
しかし、これは生まれながらに持ったものかというと、そうでもないことも分かっています。
練習や試合経験によって様々なシチュエーションでのデータが蓄積されていき、脳機能が高められ、パフォーマンスの向上へと繋がっているというケースが多いです。
実際に一般レベルの人も訓練次第では、アイハンドコーディネーションなど、視覚から得た情報を適切に脳で処理し、身体に信号を送るといった一連の動作の質が上がっていきます。
この脳機能というのは、煎じ詰めると将来の “予測能力“ に依存しています。
・バスケットボールをどれほどの力で、どの位置へ落とすとどこらへんに返ってくるか。
・ディフェンスがこのように手を出してきたとき、どこへボールを動かすべきか。
上記のようなケースは、予測精度がものを言います。そしてこの予測・判断能力は、遺伝的な要素のみではなく、複雑な状況下でタスクを同時にこなしていく事によって、鍛えることができます。
努力次第で上達する脳機能
身長やウィングスパン、裸眼の視力は、私たちにはほぼコントロール不可能です。
しかし、このような脳機能の部分に視点を移してみると、行えば能力向上が期待できるものの、あまり練習などには取り入れられておりません。
というのは、ウェイトトレーニングでは、体の成長が鏡を見れば分かり、ランメニューでは、走り終えた後の達成感など、成長が可視化され、体感できます。
対して、脳機能という観点は、特につらくもなければ、これといった前進が見えにくいため、あまり多くは、取り入れられておりません。
そのため、何か遺伝子的な要素で劣っている選手にとっては、大きなチャンスとなり得るという事です。
(NBA平均身長、平均ウィングスパン、どちらからも劣っているカリーの例のように。)
おすすめの練習法
特に最初の間は、慣れないため、カリーのようにマルチタスクでドリブルを持続するのは、非常に難しいと思われます。
カリーの専属パフォーマンスコーチから、このドリルを行う注意点としては、姿勢を一定に保つこと、テンポをキープすることが挙げられています。
まずは、小さく片手のドリブルとテニスボールを宙に浮かせ、キャッチするといった簡単なドリルから開始し、徐々に難易度を上げていきましょう。
自己流で何か別のタスクを組み合わせるのも良さそうです。
(ドリブル + アジリティー) など。
マルチタスクでの動作にて注意コントロールを鍛えることによって、試合でのパフォーマンスも上がっていきますので、ぜひ実践してみてください。
ウォリアーズ全体について
今回は簡単にカリーが行っているドリルの紹介とその科学的な効果を紹介してきました。これらは、オフシーズンやシーズン中の試合前ウォームアップで、カリー個人によって取り入れられています。
ウォリアーズ全体に目を向けてみると、シーズン中にチームとして、カリーを、そしてウォリアーズの選手達を支えていた重要な要素が他にもありました。
それが休息・睡眠管理です。
カリーの所属するウォリアーズは、チームとして休息の重要性に気付いていたようで、組織的な取り組みを約15年前から行っていたそうです。
その結果、ウォリアーズの選手たちに見違えるパフォーマンスの変化を促したようです。
それでは、何を行い、どれほど試合中のパフォーマンスに影響を与えたのかを、ベテラン、アンドレ・イグダーラの実際の試合データを用いて紹介しています。下記リンクよりチェックしてみてください。
スポーツに関する疑問を下記の質問BOXより受け付けております。科学的な観点から見た解決策を後日当ブログにて回答いたしますので、是非匿名で利用してみてください。
ウォリアーズが15年前から行っていた選手の体調管理について詳細データを元に解説。
https://m.youtube.com/watch?v=M0FwbaLVHpg